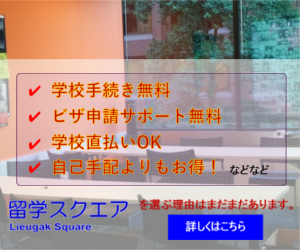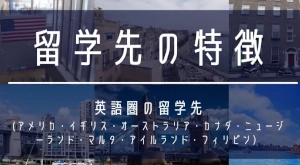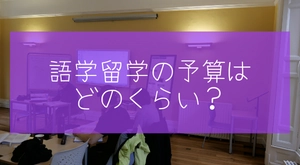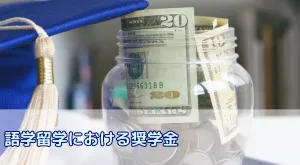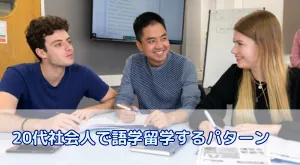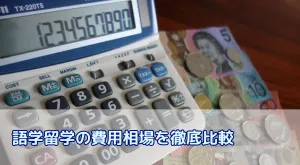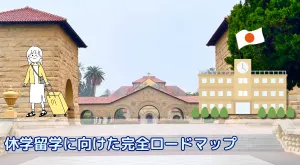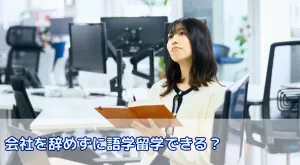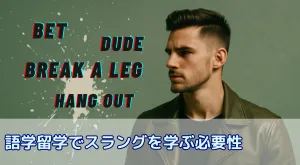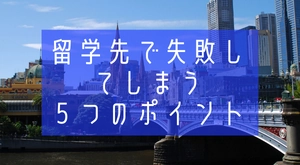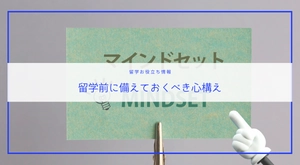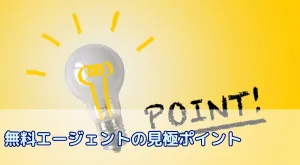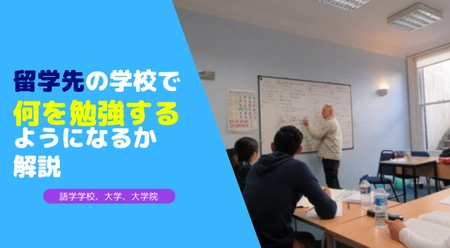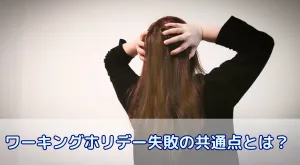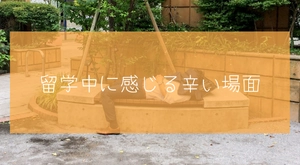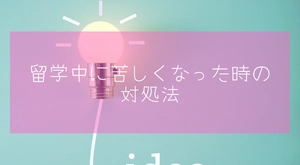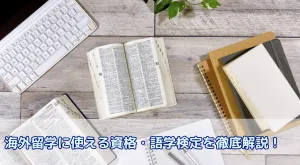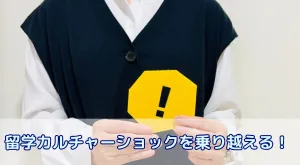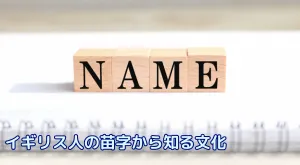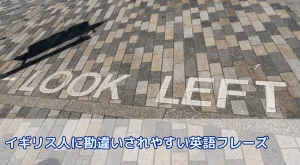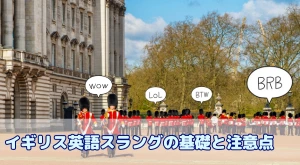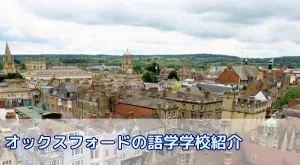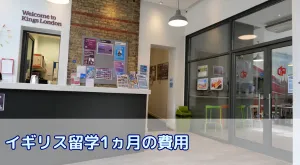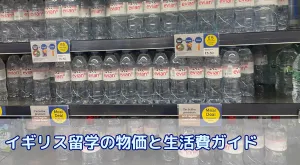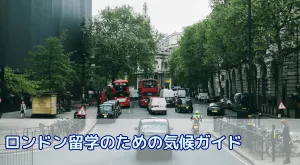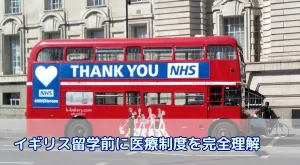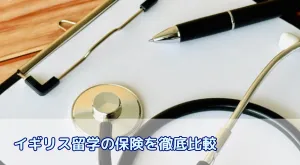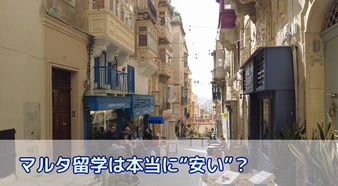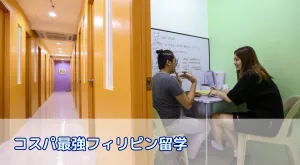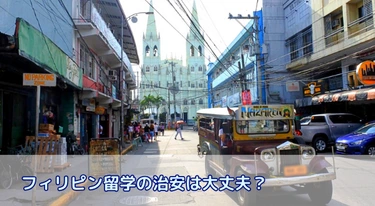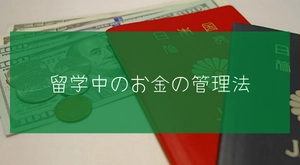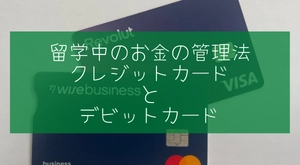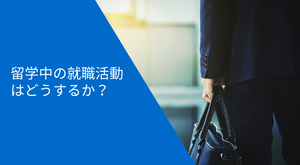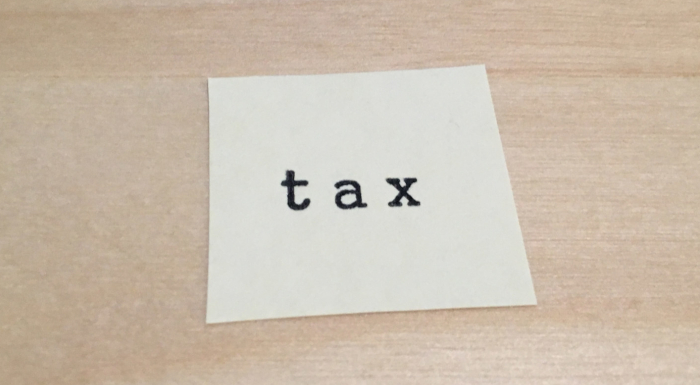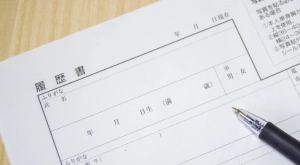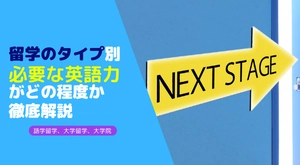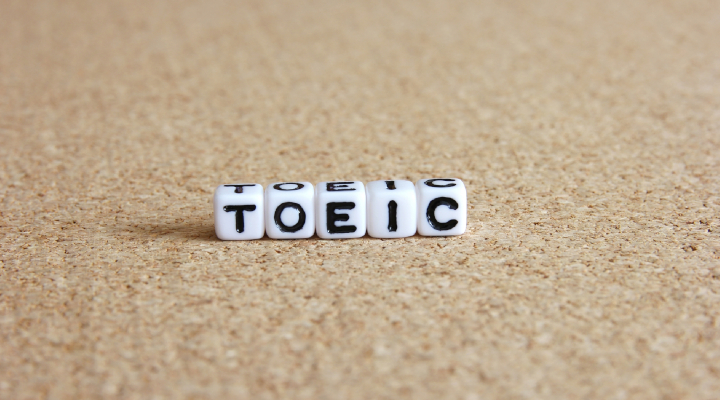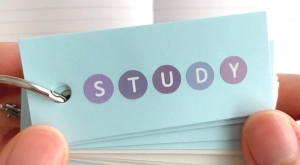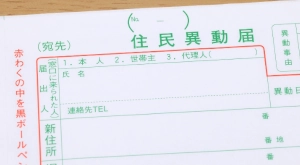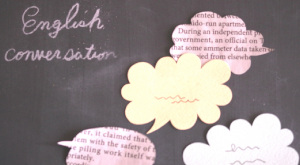スラングを学ぶ必要あるの?留学前に知っておくべき日常英会話とスラングの違いとリアル

「スラングって、留学前に勉強しておくべきですか?」そんな質問が、留学相談の中で意外と寄せられることがあります。
英語での会話力を高めたいと思う一方で、「間違って使ったら恥ずかしい」「どこまで勉強すればいいのか分からない」と感じる人も多いのではないでしょうか。
授業で習う英語と、日常のリアルな英語とのギャップ。その“ちょっとしたズレ”を埋めるヒントが、実はスラングの中にあります。
この記事では、語学学校では教わらないけれど、現地生活では避けて通れない「スラング」との付き合い方やスラングを使う上で、どんなリスクを避けるべきかを解説していきます。
語学留学でスラングは必要?実は知らないと困るリアルな理由
留学先の会話に出てくる知らない英語。
「こんなカジュアルな表現、学校じゃ習ってないけど…大丈夫かな?」と意味は何となく想像できても、使っていいのか判断がつかず戸惑ってしまう。そんな経験をした留学経験者は、決して少なくありません。
日本の英語教育ではスラングはあまり扱われず、あくまで「避けるべき言葉」として捉えられることが多いことが理由ですが、実際の留学生活では、スラングが“使えるかどうか”で、日常のコミュニケーションの質が大きく変わります。
信頼関係の「潤滑油」としてのスラング
スラングを会話に自然と取り入れることで、相手との間に信頼感と親近感が生まれます。文法的に完璧な「教科書英語」だけでは、時に堅苦しく、相手との距離を感じさせてしまうことも。スラングは、そうした壁を取り払い、お互いをより深く理解するための「潤滑油」のような役割を果たします。
日常会話に不可欠な要素
現地の日常生活では、スラングが文法よりも優先される場面が数多く存在します。スラングを知らないと、ネイティブスピーカーが使う自然な表現についていけず、会話から孤立してしまう恐れがあります。スラングを学ぶことは、現地の文化や言葉のニュアンスを理解し、よりリアルなコミュニケーションに参加するために不可欠です。
語学力と自信の向上
会話の中にスラングが自然と溶け込むようになると、それは単なる語学力の向上だけでなく、コミュニケーションに対する自信にもつながります。「この人、わかってるな」と現地の人に一目置かれることで、さらに積極的に会話を楽しめるようになり、語学学習のモチベーションも高まります。スラングを正しく使いこなすことは、現地のコミュニティに受け入れられるための第一歩と言えるでしょう。
スラングは“カジュアル英語”以上の力を持つ!現地で愛される留学生になるために
実際、大学のキャンパス、カフェ、アルバイト先、シェアハウスといった場面では、スラングを交えた会話が日常的に行われています。
「What’s up?(調子はどう?)」や「No worries(気にしないで)」などの表現は、文法的には教科書で扱われる形式とは異なるものの、日常会話においてはむしろ標準的な言い回しとして定着しています。
日本語で言うと「まじで?」「それな」などの若者言葉に近い感覚で、日本語と同じく使い方に注意は必要ですが、この“ゆるくて柔らかい言葉”こそが、人と人との心の距離をぐっと縮めてくれることがあります。
スラングを使えるメリットは?
スラングには地域性、世代感覚、価値観、さらにはユーモアのセンスまでもが含まれており、言葉の奥に文化が息づいています。
スラングを上手に使うことで次のようなメリットもあります。
- 現地の学生や友人と“自然に溶け込める”会話のテンポが手に入る
- ネイティブが「この人はわかってる」と一目置く存在になれる
- シェアハウスやアルバイトでも会話がスムーズになり関係構築が早い
- 「英語が話せる自分」という自信と自己効力感が自然に身につく
スラングの注意点は?
大切なのはスラングを「使いすぎない」こと。
スラングがどれだけ親しみやすい表現であったとしても、乱用すると印象を損ねかねません。
日本語に置き換えて考えてみてください。「それな」「マジで!」「やばい」などの言葉ばかりを繰り返す人が、知的で誠実な印象を与えるのは難しいはずです。
英語においても同様に、スラングの多用は相手に軽率な印象を与えることがあります。特に初対面や年上の相手との会話では、カジュアルすぎる言い回しが誤解を招くリスクもあります。
スラングはあくまでも、相手との関係性や場の空気を読んだうえで、適切な範囲で使い分けるべき表現の1つだということを覚えておきましょう。
日常英語とスラング、どちらも「正解」──使い分けで広がるリアルな会話力
日常英会話とスラングの違いは、「正しいかどうか」ではなく、「どの場面で、誰と、どのような関係性で使うか」という“関係性と言葉の距離”に本質があります。
| 比較項目 | 日常英会話の例 | スラングの例 | 印象の違い | 使いどき・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| あいさつ | Nice to meet you. | Sup, bro? | 丁寧で安心感がある/距離感がある | 初対面・年上相手/カジュアルな場ではやや固い |
| 感謝 | Thank you so much. | Thanks, man! | 礼儀正しい/親しみやすくフレンドリー | フォーマルな場では控える |
| 励まし | You can do it! | You got this! | 教科書的でやや直訳感/現地っぽく自然 | 仲間内やラフな雰囲気で有効 |
| 驚き | That’s surprising. | No way! / Seriously? | 落ち着いた印象/テンションが伝わりやすい | テンションや文脈に注意して使う |
| 同意 | I agree with you. | Totally / For sure | 論理的でフォーマル/自然なうなずきの印象 | ビジネスよりも日常会話向き |
(日常英語とスラングの使い分け方:具体的な表現のギャップとその意味)
表のとおり、スラングは同じ意味の言葉であっても、選び方一つで印象が大きく変わります。
たとえば「Thank you so much.」は丁寧で礼儀正しい印象を与える一方、「Thanks, man.」は親しみやすくフレンドリーなニュアンスに変わります。
また「You got this!」のような表現は、シチュエーションによっては「がんばれ」や「信じてるよ」といった励ましの言葉として、柔らかく相手に届くこともあります。
このようにスラングは、若者が使う軽い言葉ではなく、「いま、この瞬間の気持ちや空気感」をそのまま届ける、リアルな表現手段なのです。
一方で、日常英会話は初対面の人、ビジネスの相手、あるいは公的な場面では、安定した表現として機能します。
逆に、改まった場面では、スラングを使うことで「軽すぎる」と受け取られ、相手との関係性にヒビが入ってしまうリスクも否めません。
そうした時は、学校で教わったようなきちんとした表現を使った方が、誤解なく意図が伝わりやすく安心です。
「通じているのに、伝わらない」──スラングを知らないと起こるリアルな5つの壁
| 状況 | 起こりうる困りごと | その背景にある要因 |
|---|---|---|
| 学校でのグループワーク | 会話のテンポについていけず、発言しづらくなる | 仲間内で飛び交うスラングの意味がわからず、内容を正確に理解できない |
| シェアハウスでの生活 | 軽い冗談や日常会話が噛み合わず、距離感が縮まらない | 言葉の裏にあるニュアンスを読み取れず、反応が遅れる |
| アルバイト中の接客 | お客との会話がぎこちなくなり、信頼を得にくくなる | カジュアルな応対に必要な表現が不足し、硬い印象を与えてしまう |
| 現地の友人とのSNS交流 | 投稿の意味が読み取れず、話題についていけない | 短縮語やネットスラングが多用されており、文脈理解が難しくなる |
| 英語の映画・ドラマ鑑賞 | 字幕なしではセリフの本当のニュアンスが掴めない | 教科書英語では説明されない口語表現が頻出する |
(スラングを知らないことで実際に直面しやすい困りごと一覧)
留学生活が始まる前や、英語に真面目に向き合ってきた方ほど、「とりあえず文法と単語があれば何とかなる」と思ってしまいがちです。
でも、現地でのリアルな会話は、アナタの想像以上に“スラングだらけ”です。
前に紹介したような「What’s up?」「No worries」などの挨拶系スラングだけではありません。
SNS上では「LOL(laugh out loud=笑)」や「BRB(be right back=すぐ戻る)」といったネットスラングも当たり前に使われていますし、スーパーのレジやファーストフード店でも、スタッフとのちょっとしたやり取りに砕けた表現が飛び交います。
大学生同士のグループLINEでも、日本人にとっては意味がわからない略語が次々と出てくることも珍しくありません。
つまり、日常の空気感の中に自然に存在していて、誰も“難しい言葉”として意識していない英語なのです。
そんな現地の空気の中で、教科書で習った英語だけを一生懸命使おうとしても、なかなか会話のリズムに乗れません。
スラングの意味が分からなければ、返す言葉が見つからず、「えっと…」と詰まってしまい、結果的にうなずくだけで終わってしまうことも少なくありません。
英語で話すことの文法の正確さにこだわりすぎたり、「間違ってはいけない」と思うあまり慎重になりすぎると、英語を使って相手と関係を築くという本来の目的から外れてしまうリスクもあります。
実際の留学生活では、正解の英語で話すことよりも「その場でどう伝え、どう反応するか」が求められる場面の方が、ずっと多いのです。
語学学校ではスラングを教えない?標準英語の「役割」とは
- 語学学校は、国際的に通用する「標準英語」の習得を最優先にしている
- カリキュラムはTOEICやIELTSなど試験・資格対策を前提に設計されている
- ビジネス英語やアカデミック英語ではスラングは不適切とされる場面が多い
- 授業の均質性と誤解防止のため、スラングのような曖昧な表現は避けられる
- スラングは文化や世代によって変化が激しく、教科書的な扱いが難しい
語学学校でスラングを扱わないのは「教えないからではなく、教えられない事情がある」からです。
語学学校が提供する英語教育は、主に「標準英語(Standard English)」と呼ばれる、文法的に正確で誰にでも通じる英語を中心に構成されています。
この標準英語は、TOEFLやIELTSといった国際試験や、将来のビジネス英語の基礎になる言語体系です。
そのため、多くの語学学校ではまず「世界共通の英語の土台」として、この標準英語を身につけることを最優先にしています。
それが、語学留学の基本的な目的であり、多くのカリキュラムの出発点となっています。
一方、スラングは現地の日常会話に深く根付いています。
しかし、その意味は文脈によって曖昧であり、時代や地域によっても大きく変化します。
この変動性ゆえに、スラングは教科書のように「正解」を定義しづらく、英語の教え方として体系化することが非常に困難です。
語学学校では雑談の中で自然とスラングに触れる機会はあるかもしれませんが、それを正式な「授業」として教えることは基本的にありません。
実際、現地に行ってみるとわかりますが、「Cool」という一語でさえ、使う人の年齢や地域によってニュアンスがまったく異なります。
ある世代では「Cool=カッコいい」という意味で使われますが、別の世代では「皮肉」や「微妙な同意」を示すこともあります。
つまり、スラングというのは、日本語で言うところの「それな」や「マジで?」のような表現と同様、日常の空気や関係性の中で育まれるものです。
そうした言葉=スラングは、教科書では、ほぼ学べません。
スラングを本当に理解し、使いこなせるようになるには、現地の人との会話や、SNS・シェアハウス・アルバイト先など、生きた英語が飛び交う環境に身を置くことが不可欠なのです。
なぜスラング英語は英語学習で避けられがちなのか?
- 意図せず不快感や誤解を招く「失礼な表現」になるリスクがある
- 同じ言葉でも使い方を誤ると、ネガティブな意味で伝わることがある
- 試験や就職活動で「不適切な英語」と評価される恐れがある
- 相手との関係性や空気を読み間違えると、会話そのものが破綻する
語学教育の現場では、スラングは“扱いづらい英語”として意図的に避けられる傾向があります。
その背景には、使い方を誤った際の誤解やトラブルのリスクが想像以上に大きいという現実があります。
スラングは、意味だけでなく「トーン」や「文脈」に強く依存しており、 たとえば英語圏でよく使われる “Shut up!” は、親しい友人同士なら「ウソでしょ?まじで?」のような軽い驚きを表す一言ですが、関係性が浅い人に言ってしまうと「黙れ」と本気で受け取られ、相手を不快にさせてしまう危険性があります。
日本語でも「ウケる」「やばい」といった表現は、場面や相手を選ばなければ誤解を招くことがあります。
留学生の中には、英語で “That’s sick!”(=すごい!)と褒めたつもりが、「気分が悪い」と受け取られ、気まずい空気になったという“あるあるエピソード”もあるほどです。
さらに、スラングは常に変化し続ける生きた言葉です。
昨日まで通じていた表現が、今日は「古い」「ダサい」「不適切」と見なされることもあります。
また、ビジネスや就職面接、学校のプレゼンテーションなど、フォーマルな場面でスラングを使ってしまうと、「礼儀をわきまえていない」と判断されるケースも多くあります。
英語試験で使用すれば減点の対象になることもあり、キャリアに直結するリスクさえ存在します。
こうした理由から、語学学校では「スラングは教えない」という方針を取ることが多いのです。
一方で、だからこそ「スラングを使いこなせると大きな武器になる」というのも事実です。
関連記事:スラングではなく標準的な英語や語学を学ぶ語学留学全般について
よくある質問(FAQ)
Q1. 留学前にスラングを全部覚える必要はありますか?
A1. いいえ、すべてを覚える必要はありません。留学前に知っておくべきなのは「よく使われる基本的なスラング」と「場面によって使い分ける感覚」です。たとえば「What’s up?」「No worries」などの頻出表現を知っておくだけでも、現地での会話がぐっと楽になります。大切なのは「全部覚える」よりも「どういう場面で使うかを理解する」ことです。
Q2. スラングを使って失礼にならないためのコツは?
A2. コツは「相手との距離感とシーンを見極めること」です。友人同士やカジュアルな場面では自然に受け入れられますが、初対面や年上、ビジネスシーンでは避けた方が無難です。まずは“聞き取れるようになる”ことを優先し、慣れてきたら仲の良い友人との会話で少しずつ使ってみましょう。
Q3. スラングはどうやって効率よく学べますか?
A3. 現地に行ってから自然に身につけるのが最も効果的ですが、出発前に以下の方法で基礎をつけておくのがおすすめです。
- 映画やドラマを字幕付きで観て、実際の使われ方を知る
- ネイティブのSNS投稿やYouTubeをチェックする
- スラング集やアプリで、よく使われる表現だけをリストアップする
こうした準備をしておくと、現地で「聞いたことはある」という安心感が生まれ、スムーズにキャッチアップできます。
「正しい英語だけでは不安…」留学前の英語学習、迷っているならご相談ください!
留学前の英語準備、とくにスラングや会話力について「このままで大丈夫かな」と感じていませんか?
本記事では“教科書だけじゃ乗り切れない”リアルな英語学習の壁とその解決策を紹介してきました。
文法が正しくても、伝わらない英語はたくさんあります。逆に、たった一言のスラングで相手との距離がぐっと縮まる瞬間も、実際の留学生活には日常的にあります。
でも、いきなりスラングを完璧に使いこなす必要はありません。
大切なのは、ただ知識を詰め込むのではなく「どういう場面で、どう話せば、相手に気持ちが伝わるのか?」という“外国人との会話の感覚”を持つことでしょう。
それは一人で参考書を読んでいるだけでは、なかなか身につきません。
だからこそ、現地のことを知っている人や、実際に失敗も経験した先輩の話を聞くことが、最短ルートになるんです。
今のあなたにとってベストな学び方は何なのか。どこまで準備しておけば安心できるのか。
まずはその不安から、一緒に整理していきませんか?
LINE公式アカウントに登録して、あなたに合った留学準備のヒントを見つけてください!
準備は、早いほどあなたの“自信”になります。「留学前に、やっておいてよかった」と思える一歩を、ここから始めてみませんか?
▶ 公式LINEはこちらから ↓